
MK Wizardの中田です。
私はお仕事で、イベントレポートや
サイト記事のためのインタビューを行うことがございます。
先日、プロの編集の方(出版社で雑誌の編集をされていたご経験あり)にライティングの添削をしていただいた経験がありましたので
その際に修正されたポイント、webライティングで気をつけるべきポイントをご共有いたします。
目次
ライティングの心構え編

初めて読む人、前提知識のない人でも読めるように
専門的な言葉や、一般的でない言葉は注釈を入れるか、わかりやすく説明を入れるようにしましょう。
例: 「エシカル」など
疲れている読者を想定する
読んでくれる方が、十分な知識があり、親切な読者であるとは限りません。
ライティングにおいてはよく、読み手の想定として「最悪な読者」を想定しなさいと言われます。
たとえば、「深夜遅くまで残業して、ヘトヘトになって帰ってきたサラリーマン」
などを想定読者として設定すると良いでしょう。
(ただし、この設定はあなたの傷もターゲットによります)
このように、疲れている人であっても
分かりやすく負担なく読める記事を目指すことで、わかりやすい文章を書く心構えを持つことができます。
また、そもそもweb上の記事は「流し読み」されることが前提です。
たとえ流し読みされたとしても、十分に意図が伝わる文章を心がけましょう。
右手にペンを、左手にハサミを
長い文章 = 良い文章ではありません。
文章を書き終えたら、声に出してみるとそして何度もチェックをし
不要だと感じたときには、どんどん削除していきましょう。
(自分で書いた文章なのでツライですが…)
①: 基本的な表記ルールを守る

以下は、ライティングにおける基本的な表記ルールです。
こちらは絶対ではありませんが、こだわりのない方は従っておいた方が良いでしょう。
見出し内には「、」を基本いれない(記事タイトルにはOK)
これはあくまで1つの統一方法です。
こだわりがないのであれば、見出し内には「、」は入れないようにしましょう。
そのほうがスッキリと見えることが多いです。
文章内、単語で改行をしない。段落でまとめる。(変なところで改行を入れない)
文章内の区切りの良い箇所で改行をするかどうかは、掲載するメディアの文体やサイトデザインにもよります。
例えば、雑誌風の記事・デザインである場合には、文章内の単語で「改行」はあまりしないように。
段落でまとめて書いた方がマガジンとしての雰囲気を出すことができます。
ただし、情報を伝えるページ、ノウハウページ、マニュアルなどであれば
文中であっても適切な箇所で改行する事はOK。
特に、スマートフォンから読む場合を考えて
適切な箇所で改行をいれる事は、むしろ文章デザインの1つとも言えるでしょう。
「?」「!」の後はスペース(半角スペース)を入れる。
? や! の使い方において、一般的な書き方のようです。
このようにスペースを開けることで、より読みやすくなります。
なお、「」の場合は記号の後にスペースは不要。
◯ヶ月はNG。ヶは基本使わないので「カ」もしくは「か」で統一する。
この 「◯ヶ月」等の文字が、ライティング先のメディアではどのように使われているかを
事前に確認しておく方が吉でしょう。
②: 表記の揺れに気をつけて、統一する。正確に引用する。
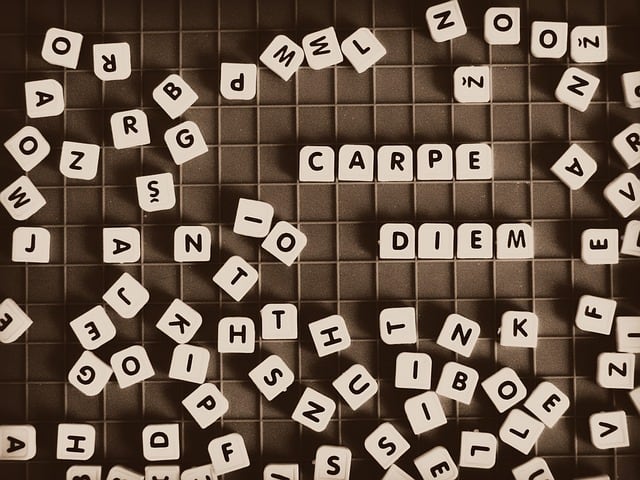
会社名、チーム名、プロジェクト名などは、全て省略せずに記載する
半角/全角英数字や、半角スペースなどにも注意。
失礼にも当たるので、厳密に合致させるようにしましょう。
文中に個人名を入れるときはフルネームで
文中に入れる個人名は、苗字だけでなく、なるべくフルネームであることが望ましいです。
ペンネームや、別の呼び方がある場合には、この限りではありません。
「とき」と「時」というように、漢字が揺れていることがあるので、注意する
最低限、1つの同じ記事内においては表記を統一するようにしましょう。
他に「こと」と「事」などもありえます。
③: あいまいな言い方はせず、勇気をもって言い切る

曖昧な表現が多いと、文章としての歯切れが非常に悪くなってしまいます。
なるべく断定的な表現を使い、リズムのある文章を心がけましょう。
「考えた、思った」などはあまり使わないほうがベター
勇気をもって言い切りましょう。結果的に、伝える内容としては同じことです。
「~のようです」「~ようでした」の伝聞形式はあまり使わない。
「という」、「というのは」はあまり使わない
「考えている」といった「~ている」は多用しない
「~してみると」の表現はNG。「みると」は省略する。
不要な表現はどんどん削っていきましょう。
「~したいな」という表現はNG。「~したい」とする。
「~なんです」という表記はNG。「~です」とする。
④: 繰り返し表現に注意する

意外と多いのが繰り返し表現パターン。
繰り返し表現があると、読者が混乱してしまいがちなので気をつけましょう。
「の」を続けすぎない
同じ単語が続くときは注意
同じ単語が出てくる場合には、どちらかを削っても問題ないことが多いです。
削ってしまうと難しい場合は、同じ意味で、異なる表現に変更しましょう。
話し言葉中には、「~と。」で終えてもOK。
「 」内の話し手セリフの表現方法として。
⑤: 読者への思いやり、負担を減らす情報整理と文章デザイン
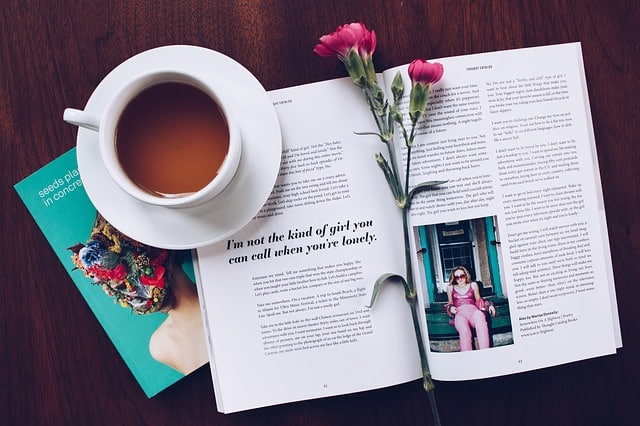
冒頭にも記載しましたが、想定読者は「残業でくたくたのサラリーマン」です。
そんな状況の読者でも、負担なく、気がついたら全部読んでしまった…となるような文章を目指していきましょう。
またある程度の漢字を「ひらく」(漢字でなくひらがなで記載する)ことで
ひらがなと漢字のバランスが整い、より読みやすくなります。
指示語(こそあど)を可能なかぎり使わない
webの文章は流し読みされることが基本です。
「この、その、あの、どの」といった指示語は
読者が追いかけていないことも多いので、可能な限り使わないように気をつけましょう。
「当時」のような表現はNG。「いつだろう?」と読み手の負担になる。
これも「こそあど」指示語と同様の表現です。
まだ「昔」などの表現にしたほうがよいでしょう。
イベントや出来事を引用することが複数あり、列挙に近い形となる場合には、それぞれ開催月を記述する
「様々な」は「さまざまな」と開き、「色々な」は「さまざまな」とする。
「訳」は「わけ」と開く。
「実は」「物理的に」といった形容副詞表現は削る。
「じゃあ」→ 「それなら」の表現に変える
ライティングとは「読者への思いやり」
いかがでしたでしょうか?
つまるところ、ライティングとは「読者への思いやり」であると言えます。
今回はプロの編集の方にチェックしてもらった内容をもとに、ライティングにおいて適用できる一般的なアドバイスとして作成いたしました。
皆様のライティングのスキルアップに役立ちますと幸いです。
Leave a Reply